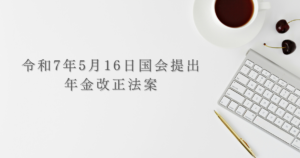2025年4月法改正② その他の法改正のポイント
2025年4月は人事労務に関する重要な法改正が多数施行されています。
前回は「育児・介護休業法」の改正点について解説しました。
今回はそれ以外の法改正について、経営者や人事労務担当者が対応すべきポイントを分かりやすく解説します。
1. 雇用保険法の主な改正点(2025年4月1日施行)
- 自己都合退職者の失業給付の給付制限期間が短縮
自己都合退職の場合、従来2ヶ月だった給付制限期間が1ヶ月に短縮されます。
また、教育訓練を受けた場合は給付制限が解除され、すぐに受給可能になります。 - 高年齢雇用継続給付の支給率引き下げ
給付率の上限が、支払賃金額の15% → 10%に引き下げられます。 - 育児時短就業給付金の創設
2歳未満の子を養育する短時間勤務者に対し、賃金の10%を支給する新たな給付金制度が始まります。
実務のポイント
- 退職者への制度変更の周知と丁寧なフォロー
- 高年齢労働者の賃金設計の見直し
- 短時間勤務者向けの雇用管理体制の強化
2. 子ども・子育て支援法の主な改正点(2025年4月1日施行)
- 妊婦支援給付の創設
妊婦に対して10万円を支給する新制度が創設されます。 - 出生後休業支援給付の創設
子の出生後、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金と合わせて手取り100%相当の給付が支給されます。
実務のポイント
- 育休取得を促進するための社内制度の整備
- 従業員への支援制度の案内と活用の推進
3. 障害者雇用促進法の主な改正点(2025年4月1日施行)
- 障害者雇用率に関する除外率の引き下げ
一部の業種に適用されていた障害者雇用の除外率が10%引き下げられ、実質的な雇用義務が強化されます。
実務のポイント
- 障害者の雇用促進と職場環境の整備
- 雇用率を満たしていない場合の対策検討
4. 高年齢者雇用安定法の改正(2025年4月1日施行)
- 65歳までの雇用確保措置の完全義務化
これまで「努力義務」とされていた65歳までの雇用確保が完全義務化されます。
企業は定年制の廃止、65歳までの定年引上げ、65歳までの継続雇用のいずれかの措置を実施する必要があります。
実務のポイント
- 継続雇用制度の見直し
- 高年齢者の処遇改善や職務設計の検討
5. 次世代育成支援対策法の改正(2025年4月1日施行)
- 行動計画策定時の状況把握・数値目標の設定が義務化
一般事業主行動計画の策定や変更の際には、育児休業等の取得状況の把握と数値目標の設定が義務となります。
実務のポイント
- 行動計画の見直しと数値目標の設定
- 計画達成に向けた具体的な取り組みの強化
6. 労働者死傷病報告などの手続きの電子申請義務化(2025年1月1日施行)
- 一部手続きの電子申請が義務化
労働者死傷病報告などの届出は、原則として電子申請が義務化されます。
なお、2025年1月~3月に発生した休業4日未満の労災については、4月から電子申請が必要です。
実務のポイント
- 電子申請の準備と運用体制の整備
- 労災発生時の報告フローの見直し
まとめ
2025年4月の改正は多岐にわたり、実務への影響も大きくなります。
企業としては、改正内容を正しく把握し、従業員への周知・制度の見直しを早めに進めることが重要です。
対応に不安がある場合は、専門家への相談をおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について」
- こども家庭庁「妊婦のための支援給付のご案内妊婦のための支援給付のご案内」
- 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
- 厚生労働省「高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了」
- 厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます」
- 厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されました」
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください